上肢機能は、食事・整容・更衣・移乗など、日常生活の多くの場面で必要とされる重要な要素です。
特に脳卒中や整形外科疾患の対象者においては、上肢の可動域・筋力・巧緻性の低下がADLやQOLの低下に直結するため、早期の評価と適切な介入が求められます。
しかし、学生や若手療法士の中には、「STEFやMFTなどの評価結果をどう読み解き、臨床判断にどう活かすべきか」に悩む場面も少なくありません。
そんな時に指針となるのが「カットオフ値」です。
カットオフ値は、上肢評価において「自立/要介助」「回復可能/介入必要」などを判定するための基準であり、介入方針や支援計画の立案に役立つ臨床的な判断材料となります。
ただし、評価法や疾患によって基準値は異なるため、すべてを記憶しておくのは困難です。
そこで本記事では、臨床現場で使用頻度の高い上肢機能評価のカットオフ値を、文献とともに一覧で整理しました。
教育・臨床・退院支援の場面で、ぜひご活用ください。
カットオフ値とは?
カットオフ値とは、ある評価指標において「リスクあり/なし」「正常/異常」などを判定するための基準値です。
臨床現場では、対象者の状態を定量的に把握し、介入の必要性や方針を判断する際の重要な指標となります。
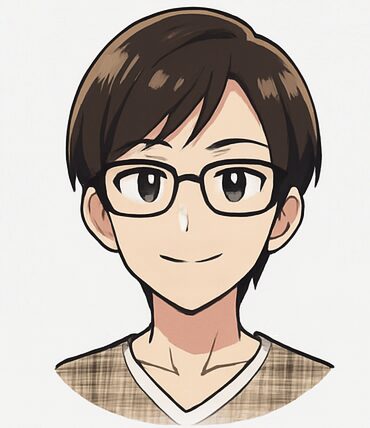
カットオフ値は、判断材料として優れた基準値ですが、「絶対的な基準」ではなく「参考値」であることに注意しましょう。

疾患・年齢・文化的背景による変動や、評価するときの椅子の高さなど、評価手技のばらつきがあることも念頭に置く必要があります。
STEF(Simple Test for Evaluating Hand Function:簡易上肢機能検査)
STEF(簡易上肢機能検査)は、10種類の物品を把持・移動する速度を評価し、巧緻性・粗大運動・指先操作を総合的に数値化する評価です。
各手ごとに最大100点満点で評価され、高得点ほど動作速度と効率が良好であることを示します。
評価時間が短く、再現性が高いため、急性期から回復期まで幅広く使用可能です。
| 対 象 | カットオフ値 | 解 釈 |
|---|---|---|
| 脳卒中患者 (急性期/麻痺側:利き手) | 50点以上 | 箸操作が自立できる可能性が高い |
| 脳卒中患者 (回復期) | 40点以上 | 食事・整容などの基本ADLにおける自立可能性あり |
| 一般高齢者 (非麻痺) | 80点以上 | 生活動作に支障なし |
📚 参考文献
- 近藤健, 関根圭介, 武田智徳, 野口直人, 李範爽
急性期脳卒中患者における上肢機能評価を用いた麻痺した利き手で箸操作が自立できる予測因子の検討
作業療法. 2019;38(3):277–284.
J-STAGE PDF(全文) - Therabby(2025)
STEF(簡易上肢機能検査)の採点と解釈|点数の見方・基準・評価指標をわかりやすく解説
記事リンク
MFT(Manual Function Test:脳卒中上肢機能検査)
MFT(脳卒中上肢機能検査)は、2000年に国立身体障害者リハビリテーションセンターが開発した、脳卒中後の麻痺側上肢の機能回復度を定量的に評価する検査です。
MFTは、上肢麻痺患者のADL自立度や在宅復帰の予測に活用される重要な指標です。
| 対 象 | カットオフ値 | 解 釈 |
|---|---|---|
| 脳卒中患者 | 24点以上 | 在宅復帰の可能性が高い |
| 脳卒中患者 (回復期) | 20点以上 | 食事・整容などのADL自立に必要な水準 |
| 脳卒中患者 (急性期/回復期) | 16点未満 | 介助・代償手段の検討が必要 |
📚 参考文献
- 徳田和宏ほか(2024)
脳卒中後上肢麻痺を呈した対象者の在宅復帰に必要な上肢機能の検討
Journal of Comprehensive Physiotherapy Research. 4:2024-009
J-STAGE PDF(全文) - therabby.com(2025)
MFT(脳卒中上肢機能検査)- 方法・注意点・解釈・カットオフ値について
記事リンク - 国立身体障害者リハビリテーションセンター(2000)
脳卒中患者の上肢機能検査(MFT)と機能的作業療法
PDFマニュアル
FMA-UE(Fugl-Meyer Assessment – Upper Extremity)
FMA-UE(Fugl-Meyer Assessment – Upper Extremity)のカットオフ値は、脳卒中後の上肢麻痺の重症度分類や介入効果の判定に活用されます。
- FMA-UEはCI療法や促通的介入の効果判定におけるゴールドスタンダード
- 得点帯による層別化は、介入方針・退院支援・生活期支援の判断材料として有効
- MCID(4.0〜12.4点)を基準に、臨床的に意味のある改善かどうかを判定可能
| 得点範囲 | 重症度分類 | 解 釈 |
|---|---|---|
| 0-22点 | 重度麻痺 | 自発的な運動はほぼ困難。 CI療法や促通的介入が必要。 |
| 23-47点 | 中等度麻痺 | 一部の随意運動が可能。 ADL動作の一部に支障あり。 |
| 48-66点 | 軽度麻痺 | ほぼ自立可能。 巧緻性や速度に課題が残る可能性あり。 |
※この分類は、臨床現場での重症度層別化や介入方針の決定に活用されます。
📚 参考文献
- 唯根弘ほか(2023)
脳卒中後の上肢機能評価における臨床的に意義のある最小変化量と最小可検変化量の検証:システマティックレビュー
作業療法. 42(5):572–580
J-STAGE PDF(全文) - FMA-UEのMCID(臨床的に意義のある最小変化量)は4.0〜12.4点と報告され、介入効果の判定に活用可能。
- Fugl-Meyer Assessment 原典(1975)
The post-stroke hemiplegic patient: A method for evaluation of physical performance
University of Gothenburg
公式解説ページ - FMAは、脳卒中後の感覚・運動障害を定量的に評価するために開発された標準化スケール。FMA-UEは上肢機能に特化したサブスケール。
- Zhou et al.(2025)
- Estimating Upper Extremity Fugl-Meyer Assessment Scores From Reaching Motions Using Wearable Sensors
Harvard Biodesign Lab
PDF(全文) - ウェアラブルセンサーによるFMA-UEの自動推定モデルを構築。遠隔評価や在宅リハへの応用が期待される。
- STROKE LAB(2024)
【令和6年版】ヒューゲルメイヤー評価法を学ぶ 上肢編/予後予測
記事リンク - FMA-UEの得点帯による重症度分類(0–22点:重度、23–47点:中等度、48–66点:軽度)を提示。臨床的な層別化に有用。
まとめ
上肢機能は、日常生活の多くの場面で必要とされる重要な要素であり、脳卒中や整形外科疾患の対象者においては、ADLやQOLの低下に直結します。
本記事では、STEF・MFT・FMA-UEを中心に、自立度や在宅復帰の予測に役立つカットオフ値を文献ベースで整理しました。
カットオフ値は、臨床判断を助ける有用な指標ですが、「絶対的な診断基準」ではなく「参考値」であることに注意が必要です。
疾患・年齢・評価手技の違いによって数値は変動するため、他の評価法との併用や臨床所見との統合的判断が求められます。
シリーズ全体を通して、教育・臨床・退院支援の現場で役立つ実践的な知識の共有を進めていきたいと思います。


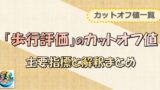
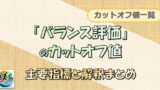
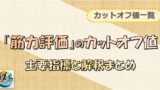
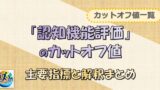
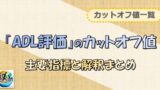
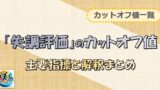
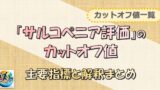
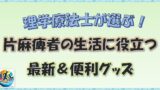
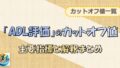
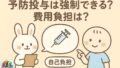
コメント