医療の現場で働くコメディカル(看護師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師など)は、患者の健康状態を適切に評価し、必要なケアを提供する役割を担っています。
そのため、バイタルサイン(Vital Signs) に関する知識は、医療従事者として欠かせません。
この記事では、コメディカルが知っておくべきバイタルサインの基本を解説し、日々の業務で活用する方法について紹介します。
バイタルサインとは?
バイタルサインとは、患者の生命活動を示す基本的な指標であり、健康状態を客観的に評価するために重要なデータです。
代表的なバイタルサインには以下の5つがあります。
これらのデータを正しく測定し、変化を見逃さないことが、適切なケアにつながります!
各バイタルサインの正常値と注意すべき変化
バイタルサインを測定する際、基準値と異常値を理解しておくことが重要です。
| バイタルサイン | 正常値 | 異常の可能性 |
|---|---|---|
| 体温 | 36.0~37.5℃ | 38℃以上(発熱) 35℃以下(低体温) |
| 脈拍 | 60~100回/分 | 50回以下(徐脈) 120回以上(頻脈) |
| 血圧 | 120/80 mmHg | 140/90 mmHg以上(高血圧) 90/60 mmHg以下(低血圧) |
| 呼吸数 | 12~20回/分 | 10回以下(徐呼吸) 25回以上(頻呼吸) |
| 酸素飽和度 | 95~100% | 90%以下(低酸素) |
バイタルサインの変化は、疾患の兆候である場合があるため、異常値を確認した際は速やかに対応する必要があります。
バイタルサイン測定のポイント
バイタルサインを測定する際は、正確な値を取得するための注意点 を押さえておくことが大切です。
日々の測定を正確に行うことで、患者の健康状態を適切に把握できます!
コメディカルの現場でのバイタルサイン活用方法
バイタルサインを活用することで、患者の状態をより深く理解し、適切な対応が可能になります。
どの職種でもバイタルサインは患者ケアの基礎となる重要な情報です!
バイタルサインの異常にどう対応するか?
異常値を発見した際には、適切な対応が求められます。
異常値の原因を考え、適切な対応を速やかに行うことが重要です!
まとめ
コメディカルにとって バイタルサインの知識は患者の健康を守るための基本 です。
日常の業務の中で正確に測定し、異常値に気づいたら適切な対応を行うことが求められます。
患者の安全と健康を守るため、バイタルサインの管理を徹底し、より良い医療ケアを提供していきましょう!

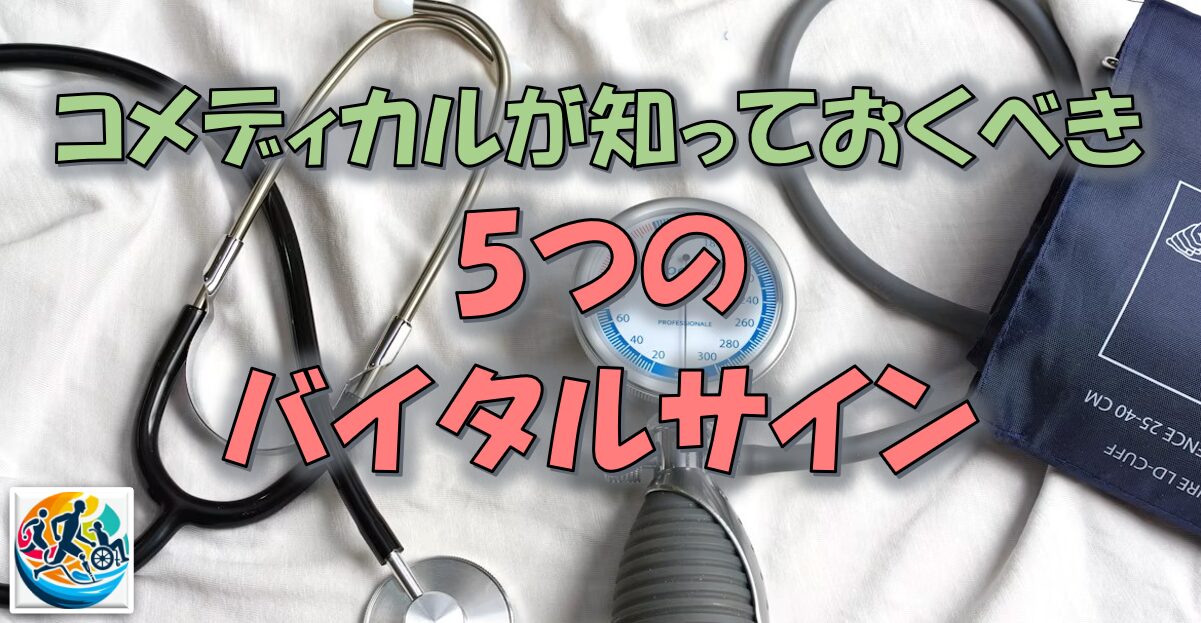
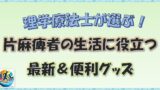

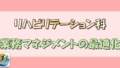
コメント