2025年7月20日、第27回参議院選挙が全国で実施されました。
今回は医療・介護分野において重要な役割を担う理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の国家資格保持者が計5名立候補。
専門職が国政に直接関与する機会として、大きな注目を集めました。
この記事では、選挙結果の整理とともに、リハビリ専門職が政治に与える影響、業界の課題や可能性について深掘りします。
リハビリ専門職立候補者一覧と選挙結果
今回の選挙では、リハビリ専門職の資格を持つ5名が選挙に立候補しました。
これは、専門職としての政治参画が徐々に広がっていることを示しており、医療現場に根ざした視点が政治に必要とされていることの象徴であると言えるでしょう。
しかし……
「第27回 参議院選挙」では、立候補者全員が落選する結果となりました。
| 氏名 | 所属政党 | 保有資格 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 田中昌史 氏 | 自由民主党 | 理学療法士 | 落選 |
| 山口和之 氏 | 日本維新の会 | 理学療法士 | 落選 |
| 渡邊雅行 氏 | 立憲民主党 | 理学・作業療法士 | 落選 |
| 中野智彰 氏 | 諸派 | 理学療法士 | 落選 |
| 金城幹泰 氏 | 参政党 | 言語聴覚士 | 落選 |
この結果は、専門職の政治参画がまだ発展途上であることを物語っています。
過去の参議院選挙におけるリハビリ専門職の立候補者数の推移
| 年(選挙回) | 立候補者・当落 |
|---|---|
| 2013年(第23回) | 小川かつみ氏が初当選 |
| 2016年(第24回) | 小川かつみ氏が再選を目指すも落選 |
| 2019年(第25回) | 小川かつみ氏が再挑戦するも落選 田中昌史氏が初出馬も落選 |
| 2022年(第26回) | 田中昌史氏が初当選(2023年1月に繰り上げ当選) 小川かつみ氏は落選 山口和之氏は落選 |
| 2025年(第27回) | 田中昌史氏、山口和之氏、渡邊雅行氏、中野智彰氏、金城幹泰氏は落選 |
傾向と考察
- 増加傾向
- 2013年以降、立候補者数は徐々に増加。2025年は過去最多の5名が出馬。
- 理学療法士が中心
- 毎回出馬しているのは理学療法士資格保持者。作業療法士・言語聴覚士は近年になって登場。
- 比例代表が主戦場
- 出馬形態はほぼ比例代表。
- 当選者は限られる
- 立候補者数は増えているが、当選者は1〜2名にとどまる。
この推移を見ると、リハビリ専門職の政治参画は着実に広がりつつあるものの、影響力の定着には時間がかかっていることがわかります。
リハビリ専門職の現状課題と政治参画の重要性
【現状の課題】
| 課題項目 | 内容 |
|---|---|
| 認知度の低さ | 「理学療法」「作業療法」などの言葉の理解が一般層に届いていない |
| 組織的戦略不足 | 業界団体の選挙戦略や支援体制が他職種と比べて弱い |
| 多職種連携の政治的表現 | リハ職と他医療職との連携を選挙戦略に活かしきれていない |
| 若手の政治参加の不足 | 現場世代による声の発信がまだ少ない |
【政治参画の重要性】
1️⃣ 現場の声を政策に反映できる
- リハビリ職は患者・利用者との距離が近く、地域社会のニーズを日々実感している。
- 制度設計に参加することで、机上の空論ではない、実態に即した政策を推進できる。
- 診療報酬、介護報酬、地域包括ケアなどの制度設計に現場目線が反映されることで、実効性の高い政策が生まれます。
2️⃣ 医療・介護制度の改善に貢献
- 診療報酬や介護報酬、地域包括ケアなど、リハビリ職が関係する制度は多岐にわたります。
- 専門職が政治に関与することで、報酬体系や職域の整備、働き方改革がより現実的になる。
3️⃣ 社会的認知と職域の拡張
- 国民のリハビリへの理解促進や教育施策の強化が可能に。
- 政治活動を通じて、「リハビリ=医療の補助」から「生活再構築の専門職」への認識転換を図れます。
- 医師や看護師に比べ、リハ職は制度的に後回しにされやすい。政治的発信力がそのギャップを埋める一歩になります。
4️⃣ 高齢社会への制度的対応
- 超高齢化が進む中、リハビリ職は在宅・地域・介護領域で不可欠な存在。
- その役割を制度レベルで確立し、持続可能な医療介護体制の構築に寄与できます。
5️⃣ 若手・現場世代の参画を促す
- 実務経験を活かした政策提案が可能な人材が増えることで、政治と現場の距離が縮まります。
- SNS・ブログ等を活用した発信力によって、新たな政治参加のかたちが生まれます。
【政治参画の手段例】
私たちリハビリ専門職が行う政治参画の手段は、以下のようなものがあります。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 立候補 | 比例代表・選挙区での直接的な関与 |
| 団体活動 | 専門職団体による政策提言や議員との連携 |
| メディア発信 | ブログやSNS等による啓発・教育活動 |
| 政策協議 | 国・自治体レベルのヒアリングや委員会参加 |
政治参画は「政治家になる」ことだけではありません。
とくにSNSやブログなどによるメディア発信は、現代社会において大きな影響力があります。
また、現場で技術的・制度的な取り組みを続けることも、間接的な政治参加の一形態と言えるでしょう。
今後のリハビリ業界への影響と展望
1️⃣ 政策提言力の低下リスク
- 国政における専門職の声が届きにくくなる可能性
- 診療報酬や介護報酬改定において、現場の実情が反映されにくくなる懸念
2️⃣ 業界団体の役割がより重要に
- 日本理学療法士協会などが政策提言の主軸となる必要性が高まる
- 政治家との連携強化やロビー活動の戦略的展開が求められる
3️⃣ 若手・現場世代の政治意識の醸成
- 「政治は遠い世界」という認識を改め、制度と現場の接点を理解する教育が必要
- 学生や若手セラピストが政策に関心を持つことで、将来的な参画者が育つ
業界の可能性と成長領域
最新の業界動向からは、政治参画以外にも成長のチャンスが広がっていることが見えます。
| 成長領域 | 内容 |
|---|---|
| テクノロジー連携 | AI・ウェアラブル・遠隔リハの普及 |
| 産業保健分野 | 高齢雇用対策などへの貢献 |
| メンタルヘルス | 身体介入を活かした心理支援への展開 |
| 産後ケア | 理学療法士によるケア事業への参入 |
| 国際展開 | アジア圏での市場開拓と技術輸出 |
今後の戦略的アプローチ
- 政策提言の多層化:議員だけでなく自治体・メディア等への提言
- 発信力の強化:SNS・ブログ・動画を通じた国民啓発活動
- 教育との接続:養成校での制度理解・政治教育の導入
- 多職種連携の可視化:医師・看護師・介護職との協働事例の発信
管理人の視点から考察
リハビリ職の本質は、単なる医療従事者ではなく「生活の再構築を支援する存在」です。
そのため、政治や制度の設計に意見を届けることは、専門職としての責務とも言えます。
私が取り組んできたExcelツールや評価シートの開発、ブログ発信などの活動も、まさに現場から制度へと橋を架ける手段です。
政治的代表が不在となった今だからこそ、こうした「知的介入と創造的提案」が業界を動かす力になるでしょう。
制度の中枢に届くような分析や提言を続けることで、将来的にはリハビリ職が制度形成の先導役となることも十分に可能と考えます。
結論:今こそ、戦略的な前進を!
「第27回参議院選挙」は、リハビリ専門職の政治参画にとって残念な結果でした。
しかし、それは同時に次なる変革への出発点です。
リハビリ職は「生活の再構築者」であり、「制度への知的パートナー」でもあります。
この意義を業界全体で見直し、次なる選挙や制度設計に向けて戦略的に動き出すべき時ではないでしょうか。

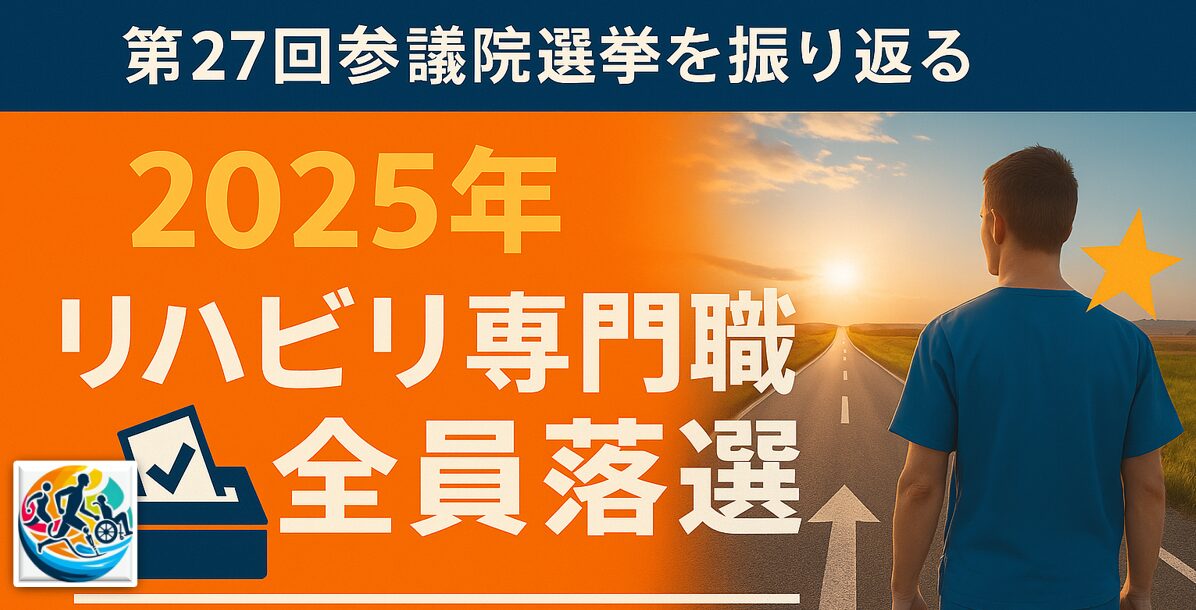



コメント