リハビリテーションにおける各種評価は、問題点の抽出や介入効果の判定に欠かせない重要なツールです。
しかし、学生や新人療法士の中には、評価結果をどう読み解き、臨床にどう活かすべきか悩む場面も少なくありません。
そんな時に指針となるのが「カットオフ値」です。
カットオフ値は、臨床判断を助ける便利な基準ですが、すべてを記憶しておくのは至難の業です。
中堅以上の療法士でも、日々の業務に追われる中で、必要な数値を都度調べるのは手間がかかります。
そこで本記事では、臨床現場で使用頻度の高い「歩行評価のカットオフ値」を、参考文献とともに一覧で整理しました。
評価の意味づけや活用のヒントとして、ぜひ日々の臨床にお役立てください。
カットオフ値とは?
カットオフ値とは、ある評価指標において「リスクあり/なし」「正常/異常」などを判定するための基準値です。
臨床現場では、対象者の状態を定量的に把握し、介入の必要性や方針を判断する際の重要な指標となります。
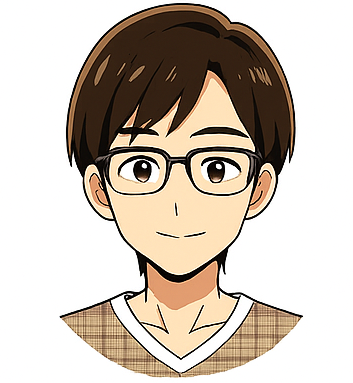
カットオフ値は、判断材料として優れた基準値ですが、「絶対的な基準」ではなく「参考値」であることに注意しましょう。

疾患・年齢・文化的背景による変動や、評価するときの椅子の高さなど、評価手技のばらつきがあることも念頭に置く必要があります。
10m歩行テスト
10m歩行テストにおける最大歩行速度と快適歩行速度のカットオフ値は、転倒リスクや生活自立度の予測に活用されます。
信頼性の高い研究では、最大歩行で1.0 m/s(10.0秒)以上、快適歩行で0.8 m/s(12.5秒)以上が重要な指標とされています。
| 評価項目 | カットオフ値 | 解 釈 |
|---|---|---|
| 最大歩行速度 | 1.0 m/s未満 | 転倒リスク増加 信号横断困難 |
| 快適歩行速度 | 0.8 m/s未満 | 屋外歩行自立困難 |
| 快適歩行速度 | 0.4 m/s未満 | 屋内歩行のみ可能 |
【最大歩行速度】のカットオフ値
最大歩行速度のカットオフ値としては、「1.0 m/s以上」が転倒予防や社会的自立の指標とされることが多く、信号横断や屋外移動の安全性を判断する目安になります。
- 飯田修平ほか(2017)の研究では、最大歩行速度が1.0 m/s以上であることが転倒予防の指標として有効であると示されています。
- 最大歩行速度は加齢による低下が顕著で、快適歩行よりも早期に機能低下を示す指標とされています。
【快適歩行速度】のカットオフ値
- Fritz & Lusardi(2009)のレビューでは、0.8 m/s未満が「屋外歩行困難」の指標として示され、1.0 m/s以上が「信号横断可能」な速度とされています。
- Middleton et al.(2015)は、快適歩行速度が0.8 m/s未満の高齢者は転倒リスクが高いと報告しています。
📚 参考文献
- 飯田修平ほか. 「10m歩行テストの信頼性:最速歩行と通常歩行の計測順序の違いによる影響」. 理学療法科学, 32(1): 81–84, 2017. J-STAGE原著論文
- Fritz S, Lusardi M. “White Paper: Walking Speed: The Sixth Vital Sign.” Journal of Geriatric Physical Therapy, 32(2): 46–49, 2009. PubMed
- Middleton A, Fritz SL, Lusardi M. “Walking speed: the functional vital sign.” Journal of Aging and Physical Activity, 23(2): 314–322, 2015. PubMed
TUG(Timed Up and Go)
TUG(Timed Up and Go)テストのカットオフ値は、転倒リスクや移動能力の評価において「13.5秒以上」が高齢者の転倒リスクを示す代表的な基準とされています。
| 対 象 | カットオフ値 | 解 釈 |
|---|---|---|
| 一般高齢者 | 13.5秒以上 | 転倒リスクあり |
| 運動器不安定症 | 11秒以上 | 診断基準の一つ |
| ADL自立困難 | 20秒以上 | 屋内ADL自立が難しい |
TUGのカットオフ値
- Podsiadlo & Richardson(1991)の原著では、「13.5秒以上」が転倒リスクのカットオフ値として示されています。
- 脳卒中患者では、TUGが「20秒」を超えると屋外歩行や自立生活が困難になる可能性があると報告されています。
※ 疾患別の補正が必要で、齢・症状に応じた解釈が求められます。
📚 参考文献
- Podsiadlo D, Richardson S. “The Timed Up & Go: a test of basic functional mobility for frail elderly persons.” J Am Geriatr Soc, 39(2): 142–148, 1991. PubMed
- 倉島謙吾ほか. 「脳卒中患者におけるTUG測定の快適速度と最大速度の検討」. CiNii Research 論文概要
- 我満衛ほか. 「TUGに影響を与える運動機能因子の検討」. 日本高齢者運動科学会誌, 41(5): 586–592, 2016. J-STAGE原著論文
6分間歩行テスト(6MWT)
6分間歩行テスト(6MWT)のカットオフ値は疾患や目的によって異なりますが、一般的に「400m未満」が高齢者の転倒リスクやADL低下の指標とされます。
心疾患や呼吸器疾患では「300〜350m未満」がリスク群とされることが多いです。
| 対 象 | カットオフ値 | 解 釈 |
|---|---|---|
| 一般高齢者 | 400m未満 | ADL低下・転倒リスクあり |
| 心不全患者 | 300m未満 | 予後予測不良・再入院リスク |
| COPD患者 | 317~350m未満 | 運動耐用能低下・酸素療法の検討 |
| 肺高血圧症 | 440m以下(中リスク) 165m未満(高リスク) | 予後予測に使用 |
| 回復期リハ患者 | 200m以上 | 自立歩行・退院可能性の目安 |
| 屋外歩行の可否 | 213m以上 | 屋外歩行が可能(自立生活の目安) |
📚 参考文献
- 佐竹將宏ほか. 「6分間歩行試験について」. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌, 28(2): 286–290, 2019. J-STAGE
- Cahalin LP et al. “The six-minute walk test predicts peak oxygen uptake and survival in patients with advanced heart failure.” Chest, 110(2): 325–332, 1996. PubMed
- ATS Statement. “Guidelines for the six-minute walk test.” Am J Respir Crit Care Med, 166(1): 111–117, 2002. ATS Guidelines
- Miyamoto S et al. “Prognostic value of 6MWT in primary pulmonary hypertension.” Am J Respir Crit Care Med, 161(2): 487–492, 2000. PubMed
- 鋤崎利貴ほか. 「6分間歩行テストの再現性の検討」. CiNii Research, 長崎大学医学部, 2020. CiNii
- Enright PL, Sherrill DL. “Reference equations for the six-minute walk in healthy adults.” Am J Respir Crit Care Med, 158(5): 1384–1387, 1998. PubMed
まとめ
歩行評価は、リハビリテーションの中でも実施頻度が高く、退院後の生活を見据えた支援において重要な指標です。
評価結果とカットオフ値を照らし合わせることで、患者さんの身体機能や動作能力をより正確に把握することが可能になります。
ただし、カットオフ値は「絶対的な基準」ではなく、あくまで「参考値」であることを忘れてはなりません。
退院後の生活を検討する際には、他の評価結果や生活背景とあわせて総合的に判断することが重要です。
各種評価とカットオフ値を適切に活用することで、より質の高い、個別性のあるリハビリテーションの提供につながるでしょう。

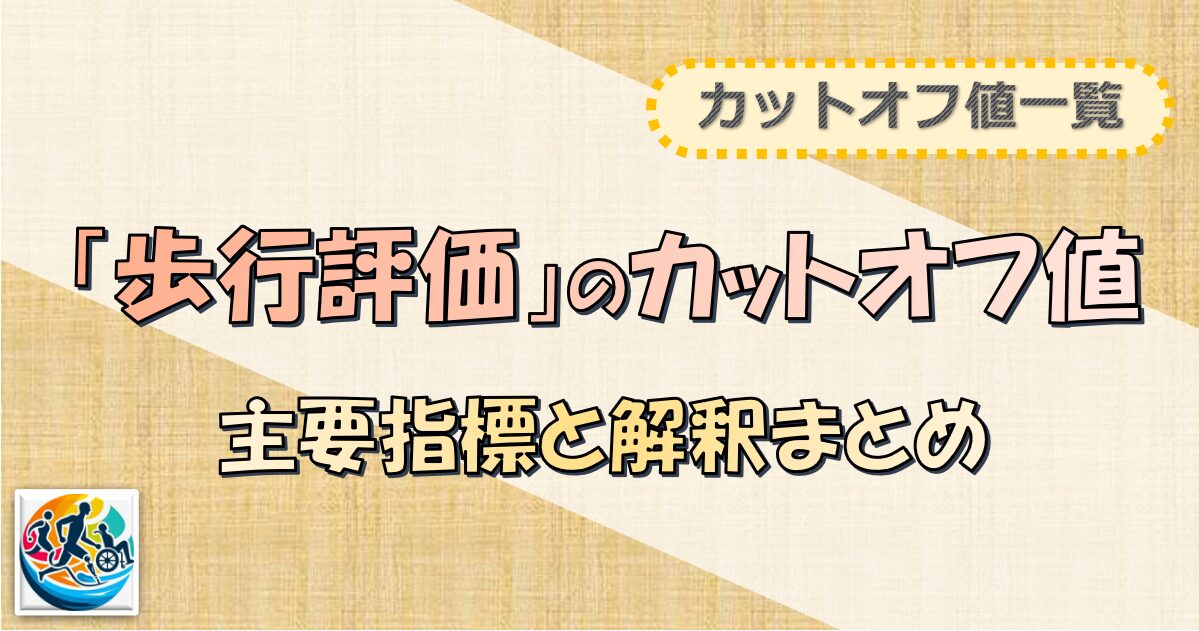
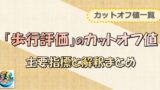
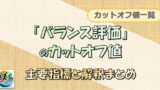
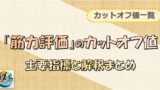
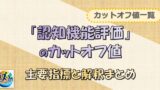
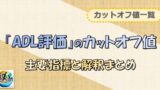

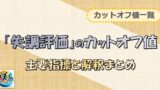
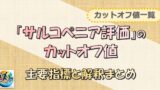
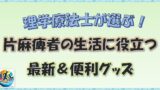


コメント