
理学療法士として20年、医薬品関連の株に投資をはじめて10年、リハビリテーション関連のエビデンスの低さがずっと気になっていました。
医薬品が市場に出回る(上市という)まで、実に多くの研究データと治験による効果・安全性の認可といった高いハードルをクリアする必要があり、医薬品を用いた治療には当然ながら高いエビデンスがあります。
しかし、リハビリテーションにおけるエビデンスのフタをあけてみると、その内容は医薬品のそれには到底及ばないと感じます。
ではなぜ、リハビリテーションのエビデンスは低いと感じるのか?考えていきたいと思います。
医療の世界では、治療の有効性を評価するために エビデンス(科学的根拠) が重視されます。
特に、医薬品を用いた治療では、厳密な臨床試験や統計データに基づいてその効果が証明されます。
一方、リハビリテーションは 個別性が高く、標準化が難しいため、医薬品ほど明確なエビデンスが確立しづらいという課題があります。
この記事では、医薬品治療とリハビリテーションのエビデンスを比較し、リハビリテーションのエビデンスが低い理由や、それを改善するための課題について考えていきます。
医薬品治療のエビデンスとは?
医薬品は厳格な臨床試験を経て、その効果や安全性が証明されます。
特に「ランダム化比較試験(RCT)」や「二重盲検試験」などの手法によって、統計的に有効性を証明できることが特徴です。
このような手法を用いることで、投与量・副作用・効果の持続時間 などが詳細に評価されます。
医薬品は化学的に調合されており、治療効果が比較的安定しているため、一定の条件下で再現性が高く、信頼性のあるエビデンスが得られやすいと考えます。
リハビリテーションのエビデンスが低い理由
リハビリテーションは、医薬品治療とは異なる性質を持ちます。
そのため、エビデンスの確立が難しくなる要因があると考えます。
介入方法が多様で統一されていない
リハビリテーションでは、患者ごとに異なる介入が必要になります。
例えば、脳卒中患者の運動療法においても、回復度・年齢・併存疾患 によってリハビリのプログラムが変わります。
そのため、介入の標準化が困難 であり、一律の治療効果を証明しにくいと考えます。
「定量化」が困難
医薬品は「mg単位」で投与量を測定できますが、リハビリの介入量は「運動強度」や「回数」で表されます。
しかし、リハビリは個々の患者に合わせて治療が変化するため、どの程度の負荷が適切かを明確に定量化しにくい という課題があります。
二重盲検試験ができない
医薬品では、患者も医師も薬の種類を知らずに投与する「二重盲検試験」が可能ですが、リハビリはセラピストが直接患者に介入するため、治療内容を隠して試験することができません。
その結果、治療効果を客観的に評価しにくい状況が生まれます。
外部要因の影響が大きい
リハビリの効果は、患者の心理状態や生活環境 によって大きく変わります。
例えば、家族のサポートがある患者とない患者では回復速度に違いが生まれ、治療効果を一定条件下で評価するのが難しくなると考えます。
長期間の評価が必要
医薬品は短期間で効果が測定できる場合が多いですが、リハビリは 継続的な治療が必要 です。
そのため、長期の追跡調査が求められ、エビデンスを確立するのに時間がかかるという課題があります。
研究資金とリソースの不足
医薬品研究は製薬会社による多額の投資が背景にありますが、リハビリテーション分野の研究では同等の資金が確保されにくい場合があります。
結果として、リハビリテーション研究の規模が小さくなり、大規模で信頼性の高いエビデンスが蓄積されにくい現状があります。
リハビリのエビデンスを向上させるための取り組み
リハビリテーションの科学的根拠を強化するためには、以下のような取り組みが重要と考えます。
これらの取り組みにより、リハビリのエビデンスの信頼性を向上させることができると考えます!
医薬品治療とリハビリテーションの組み合わせ
最近では、医薬品治療とリハビリを併用することで、より効果的な治療が可能になるケースも増えています。
医薬品の即効性とリハビリの継続的な効果を組み合わせることで、より最適な治療が実現できる可能性があります。
まとめ
リハビリテーションのエビデンスが低い理由は、介入の個別性・定量化の困難さ・外部要因の影響によるものと考えます。
しかし、近年のデータ分析技術の発展により、リハビリの科学的根拠を向上させる取り組みが進んでいます。
今後は、標準化された評価指標の開発やデジタル技術の活用により、リハビリテーションのエビデンスがより強固なものになっていく必要があると感じます。
患者さんの健康を守るために、今後も研究と技術革新が求められていると思います。
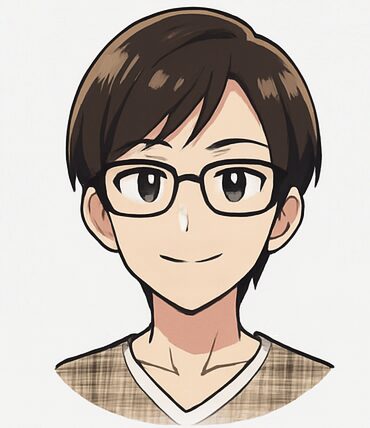
リハビリと医薬品による治療には、それぞれの強みと役割があり、互いを補完する存在!
エビデンスが低いと感じる背景には、エビデンスの質や量の違いが影響しているかもしれませんが、それは必ずしも価値を低くするものではありません。
リハビリテーション分野の現状に気づき改善を求める視点が、将来のリハビリ医療の発展に繋がっていくのだと思います!


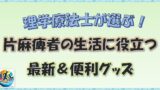


コメント