「リハビリって、いつまで続けられるの?」
「150日を過ぎたら、もう受けられないの…?」
このような不安を抱えている方も少なくありません。
実は、医療保険を使って受けられるリハビリテーション(疾患別リハビリ)には、病名ごとに期限の上限が設けられています。
この記事では、そんな「150日ルール」の正体と、終了後の選択肢について厚生労働省の制度に基づいて分かりやすく解説します。
この記事は2025年時点での制度に基づき作成されており、参考資料には厚生労働省の公式ガイドラインを使用しています。
具体的な対応については、必ず主治医などの専門職にご相談ください。
疾患別リハビリテーションとは? 医療保険の対象となる期間制限
医療機関で行うリハビリは、疾患ごとに分類され、厚生労働省が設定する「算定期限内」であれば医療保険の対象となります。
| リハビリ区分 | 主な対象疾患 | 原則の上限日数 |
|---|---|---|
| 運動器リハビリ | 骨折・関節疾患・靱帯損傷など | 150日 |
| 脳血管疾患リハビリ | 脳梗塞・脳出血・パーキンソン病など | 180日 |
| 心大血管リハビリ | 心筋梗塞・心不全・開心術後など | 150日 |
| 呼吸器リハビリ | COPD・間質性肺炎・手術後肺障害など | 90日 |
| 廃用症候群リハビリ | 長期臥床による筋力低下など | 120日 |
起算日(:医療保険でのリハビリが可能となる日)は、手術日、発症日、もしくは急性増悪日からカウントされます。
150日を超えたら、もうリハビリはできないの?
いわゆる「150日ルール」はよく聞かれる用語ですが、実際には”条件を満たせば”期限を超えてもリハビリは継続可能です。
🔹延長が認められる条件
- 医師の医学的判断により、「回復の見込みがある」とされた場合
- 月13単位(1単位=20分)の上限内で、引き続き医療保険を適用
- 処方や診療報酬の条件に基づき、必要に応じて定期的評価あり
つまり「完全に打ち切り」ではなく、条件つきの継続が制度内で認められています。
ただし、継続できるかどうかは医療機関の方針や診療報酬制度の運用状況によって左右されるため、必ず医師と相談してください。
💡よくある誤解と注意点
- 「150日きっかりで終了」とは限らない
- リハビリの種類・診断名・回復状況により、上限日数に個人差があります。
- また、複数のリハビリが併用されるケースもあり、算定ルールが複雑な場合も。
- 期限後も回復の支援はできる
- 医療保険の枠を超えても、介護保険や自費によるリハビリで対応が可能。
- ただし、それぞれに条件や費用負担が異なります。
医療保険の期限後の選択肢とは?
1. 介護保険でのリハビリに切り替える(通所・訪問)
- 対象
- 65歳以上、または40歳以上で特定疾病がある方
- 利用には要介護(または要支援)認定が必要
- サービス例
- 通所リハビリ(デイケア)、訪問リハビリなど
- 特徴
- 生活動作の維持・向上を目的とした支援に重点
要介護認定には通常1〜2ヶ月の手続き期間がかかるため、医療保険の期限が近づいたら早めの相談がおすすめです。
2. 自費リハビリを利用する
- 保険適用外のため全額自己負担
- 専門職によるマンツーマンリハビリなど自由度が高い
- 料金例:1回60分 8,000〜15,000円前後が相場
- 対象:若年層や介護保険対象外の人に有用
📌 実際に準備しておくべきこと
- 医療保険の算定期限を事前に確認
- 主治医・リハビリ担当者にリハ継続の見通しを相談
- 介護保険の申請タイミングを逆算して準備
- 自費リハビリの事業所も比較検討しておく
まとめ
- 医療保険でのリハビリには疾患別に上限日数が定められている
- 「150日ルール」は誤解されがちだが、条件つきでの延長も可能
- 上限到達後も、介護保険・自費リハビリなど柔軟な選択肢がある
- 重要なのは、早めの情報収集と医療・介護専門職との連携
📚 参考資料・出典
- 厚生労働省|診療報酬の算定構造と疾患別リハビリの概要
- 独立行政法人 医療情報センター|リハビリ提供体制に関するQ&A
- 全国医療ソーシャルワーカー協会|介護保険と医療保険の切り替えに関する実践ガイド
制度は変更される場合があるため、最新情報は厚労省や自治体のHP、主治医に確認してください。

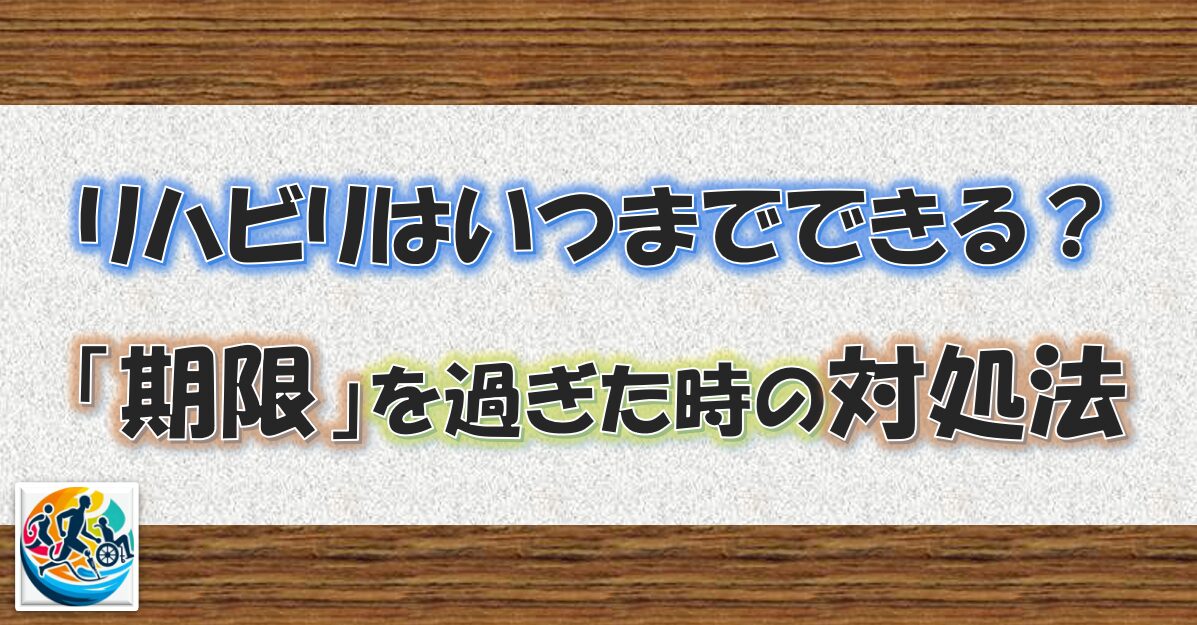

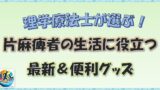

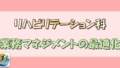

コメント